影の薄いカードの使い方を考えてみた。その1《不死の霊薬》
2010年7月5日 MTG コメント (4)
はい、M11のカードもかなりの数が公開されて、ようやくその全貌が明らかになってまいりました。
全体的に単体でハイスペックなカードが大量ですね。また、過去のカードのリメイクやメカニズムの再録も含まれていて、基本セットなのに時のらせんみたいな感じがして楽しいです。
でもそんな中に、いまいち使い道のわからないカードも紛れ込んでいますね。「え、これどうやって使うの?」「なんでこんなカードを収録するの?」と言われそうな影の薄いカードたち。
ですが、ウィザーズの人たちはかなり計画的に収録カードを決めているので、使い道の無いカードを収録することはまず無く、何かしら意味があると思います。
そこで、そんなM11に収録された影の薄いカードの利用法を考えてみました。
というわけで、今回のお題はコレ。
普通に使えば、3マナかけて5点のライフを得るだけのカードです。
アーティファクトのライフゲインとしては、以前に比べれば悪くないコストパフォーマンスになりましたが、いかんせんやることがライフゲインだけでは地味すぎます。尖った高速ビート対策のサイドボードとしてならライフゲインは効果的なものの、それ以外に何もしてくれないので、結局他のビート対策カードの方が優先されます。
そしてライブラリーへ戻る効果が何故か付いています。
通常この手の効果が付く理由は、《ダークスティールの巨像》や《真実の解体者、コジレック》のように強力なクリーチャーを簡単にリアニメイトできないようにするためか、《不死の標》などの標サイクルのように繰り返し使えるということを売りにするためかの、どちらかです。1マナと軽い《不死の霊薬》にこの効果が付いているのは、恐らく後者の理由だと考えられますが、しかし、ライフゲインしかしてくれないこのカードがライブラリーに戻っても嬉しくありません。
これだけでは構築ではおろかリミテッドですらお呼びはかかりません。
何かしら効果的な使い方はないでしょうか。
では、このカードのそれ以外の特徴に注目してみましょう。
・1マナのアーティファクト、通称ほぞである
・解決に際して墓地をライブラリーに加えて切り直す
というところです。
これらの特徴から《不死の霊薬》の使い方を考えてみましょう。
まず1マナのアーティファクトであるという点。
M11では《不死の霊薬》以外にも《脆い彫像》というクリーチャー除去用のほぞアーティファクトが収録されています。これは、ミラディンの傷痕でのほぞメカニズムの再録に期待が膨らみますね。また、アラーラの断片には軽量のアーティファクトと相性の良い《求道者テゼレット》がいます。
このような軽量のアーティファクトを有効活用できるデッキと言えば・・・そう、『テゼレッター』です。
一応テンプレート的な説明をしておくと、『テゼレッター』とは上記の《テゼレット》を軸とした青系のコントロールデッキで、旧エクテンで活躍していました。《テゼレット》や《粗石の魔道士》のサーチ能力によるシルバーバレットによる対応力の高さが強みです。
(ってwikiに書いてあった。)
しかし今月のローテーションに伴い、《テゼレット》と相性の良いミラディンの軽量アーティファクトが多数落ちたため、現エクテンでは実質的に構築不可能になっています。アラーラのアーティファクトだけでは力不足なので、ミラディンの傷痕に期待ですね。
さてさて、『テゼレッター』のようなデッキに入ることを考えると、《不死の霊薬》の評価が変わってきます。
まず、尖った高速ビートダウン相手になら、一枚挿しのシルバーバレットになります。
5点という回復量は、火力で言えばカード1~2枚分でしかありません。それだけなら《陽光の呪文爆弾》と同じです。継続的に回復できるのならばともかく、使い切りでは対策にはなりません。
そう、継続的に回復できるのならばともかく・・・です。
そこで《不死の霊薬》の二つ目の効果、ライブラリーへ戻る効果が差別化に繋がります。何度使ってもライブラリーに戻っていくので何度でもサーチしなおすことができ、《テゼレット》を放置すると毎ターン2マナで5点のライフを得られることになります。サーチだけしておいて、相手のターン終了時に余ったマナで回復すれば、尖ったデッキなら2~3回も起動できれば削り切れないライフになるでしょう。
また、《呪文爆弾》と違いコストに生け贄を含まないので、能力にスタックしてアンタップさせれば複数回起動させることが可能です。同じくM11で収録が発表された《通電式キー》と組み合わせれば、毎ターン10点のライフが得られます。
と、ここまでは《不死の霊薬》のいわば「おまけ」の部分です。
《不死の霊薬》の使い方の本質は他の部分にあります。
それが、もう一つの特徴である解決に際して墓地をライブラリーに加えて切り直すことを生かした使い方です。一枚挿しの多いサーチ前提のデッキであればこの効果が重要になります。
シルバーバレット戦術は確かに柔軟性があって強力ですが、厚みがありません。サーチ前提なので対策カードはそれぞれ1~2枚ずつしか入っておらず、使い切ったり対処されたりすると次がなくなってしまいます。その厚みも持たせるために、『テゼレッター』では墓地のアーティファクトを継続的に回収できる《アカデミーの廃墟》を採用しています。
そこで白羽の矢が立つのがこの《不死の霊薬》です!
特定の相手に有効なカードを一枚挿しておき、相手に応じて《テゼレット》でサーチして場に出します。相手がようやくそれを対処できたところで、《不死の霊薬》によってそのカードを墓地からライブラリーに戻し、再びサーチして場に出しましょう。相手はどんな顔をするか、楽しみではありませんか。このような《不死の霊薬》の動きによって、デッキの中の一枚挿しの枚数を水増しすることが可能になるのです。
理由は違いますが、サーチ前提の一枚挿しと墓地回収によるライブラリー修復というエンジンは、以前受信したウギンの目とエルドラージの使い方にも通じるところがありますね。
(http://mtg2384.diarynote.jp/201005232206083711/)
そして上記の通り、不十分とは言え《不死の霊薬》自体が単体でも高速ビートダウンに対する対策カードとして効果があるのが素晴らしいところです。
つまりこの《不死の霊薬》は、『テゼレッター』などのサーチ前提の一枚挿しの多いデッキに厚みを持たせるためのカードだということです。
・・・いや、やっぱ無理がありますね、すんません。
高速ビートなら《テゼレット》は一蹴されるし、墓地とライブラリーを回すより釣った方が早いし。
何より《不死の霊薬》をサーチしたいと思えない。
でもこれ以外に《不死の霊薬》の効果の意味が見つからんかったんだ・・・
教えてえろいひと!
全体的に単体でハイスペックなカードが大量ですね。また、過去のカードのリメイクやメカニズムの再録も含まれていて、基本セットなのに時のらせんみたいな感じがして楽しいです。
でもそんな中に、いまいち使い道のわからないカードも紛れ込んでいますね。「え、これどうやって使うの?」「なんでこんなカードを収録するの?」と言われそうな影の薄いカードたち。
ですが、ウィザーズの人たちはかなり計画的に収録カードを決めているので、使い道の無いカードを収録することはまず無く、何かしら意味があると思います。
そこで、そんなM11に収録された影の薄いカードの利用法を考えてみました。
というわけで、今回のお題はコレ。
Elixir of Immortality/不死の霊薬 (1)
アーティファクト アンコモン
(2),(T):あなたは5点のライフを得る。不死の霊薬とあなたの墓地をライブラリーに加えて切り直す。
普通に使えば、3マナかけて5点のライフを得るだけのカードです。
アーティファクトのライフゲインとしては、以前に比べれば悪くないコストパフォーマンスになりましたが、いかんせんやることがライフゲインだけでは地味すぎます。尖った高速ビート対策のサイドボードとしてならライフゲインは効果的なものの、それ以外に何もしてくれないので、結局他のビート対策カードの方が優先されます。
そしてライブラリーへ戻る効果が何故か付いています。
通常この手の効果が付く理由は、《ダークスティールの巨像》や《真実の解体者、コジレック》のように強力なクリーチャーを簡単にリアニメイトできないようにするためか、《不死の標》などの標サイクルのように繰り返し使えるということを売りにするためかの、どちらかです。1マナと軽い《不死の霊薬》にこの効果が付いているのは、恐らく後者の理由だと考えられますが、しかし、ライフゲインしかしてくれないこのカードがライブラリーに戻っても嬉しくありません。
これだけでは構築ではおろかリミテッドですらお呼びはかかりません。
何かしら効果的な使い方はないでしょうか。
では、このカードのそれ以外の特徴に注目してみましょう。
・1マナのアーティファクト、通称ほぞである
・解決に際して墓地をライブラリーに加えて切り直す
というところです。
これらの特徴から《不死の霊薬》の使い方を考えてみましょう。
まず1マナのアーティファクトであるという点。
M11では《不死の霊薬》以外にも《脆い彫像》というクリーチャー除去用のほぞアーティファクトが収録されています。これは、ミラディンの傷痕でのほぞメカニズムの再録に期待が膨らみますね。また、アラーラの断片には軽量のアーティファクトと相性の良い《求道者テゼレット》がいます。
Tezzeret the Seeker/求道者テゼレット (3)(U)(U)
プレインズウォーカー 口 テゼレット
[+1]:最大2つまでのアーティファクトを対象とし、それらをアンタップする。
[-X]:あなたのライブラリーから、点数で見たマナ・コストがX以下のアーティファクト・カードを1枚探し、それを戦場に出す。その後、あなたのライブラリーを切り直す。
[-5]:ターン終了時まで、あなたがコントロールするアーティファクトは5/5のアーティファクト・クリーチャーになる。
4
このような軽量のアーティファクトを有効活用できるデッキと言えば・・・そう、『テゼレッター』です。
一応テンプレート的な説明をしておくと、『テゼレッター』とは上記の《テゼレット》を軸とした青系のコントロールデッキで、旧エクテンで活躍していました。《テゼレット》や《粗石の魔道士》のサーチ能力によるシルバーバレットによる対応力の高さが強みです。
(ってwikiに書いてあった。)
しかし今月のローテーションに伴い、《テゼレット》と相性の良いミラディンの軽量アーティファクトが多数落ちたため、現エクテンでは実質的に構築不可能になっています。アラーラのアーティファクトだけでは力不足なので、ミラディンの傷痕に期待ですね。
さてさて、『テゼレッター』のようなデッキに入ることを考えると、《不死の霊薬》の評価が変わってきます。
まず、尖った高速ビートダウン相手になら、一枚挿しのシルバーバレットになります。
5点という回復量は、火力で言えばカード1~2枚分でしかありません。それだけなら《陽光の呪文爆弾》と同じです。継続的に回復できるのならばともかく、使い切りでは対策にはなりません。
そう、継続的に回復できるのならばともかく・・・です。
そこで《不死の霊薬》の二つ目の効果、ライブラリーへ戻る効果が差別化に繋がります。何度使ってもライブラリーに戻っていくので何度でもサーチしなおすことができ、《テゼレット》を放置すると毎ターン2マナで5点のライフを得られることになります。サーチだけしておいて、相手のターン終了時に余ったマナで回復すれば、尖ったデッキなら2~3回も起動できれば削り切れないライフになるでしょう。
また、《呪文爆弾》と違いコストに生け贄を含まないので、能力にスタックしてアンタップさせれば複数回起動させることが可能です。同じくM11で収録が発表された《通電式キー》と組み合わせれば、毎ターン10点のライフが得られます。
と、ここまでは《不死の霊薬》のいわば「おまけ」の部分です。
《不死の霊薬》の使い方の本質は他の部分にあります。
それが、もう一つの特徴である解決に際して墓地をライブラリーに加えて切り直すことを生かした使い方です。一枚挿しの多いサーチ前提のデッキであればこの効果が重要になります。
シルバーバレット戦術は確かに柔軟性があって強力ですが、厚みがありません。サーチ前提なので対策カードはそれぞれ1~2枚ずつしか入っておらず、使い切ったり対処されたりすると次がなくなってしまいます。その厚みも持たせるために、『テゼレッター』では墓地のアーティファクトを継続的に回収できる《アカデミーの廃墟》を採用しています。
Academy Ruins/アカデミーの廃墟しかしその《アカデミーの廃墟》の収録されている時のらせんも、秋にはミラディンの傷痕と入れ替わりで落ちてしまいます。ローウィン~ゼンディカーにも墓地のアーティファクトを回収できるカードはいくつかありますが、単体では使いづらいカードか、《蔵の開放》《覇者シャルム》などのコンボ向けのカードかの、どちらかしかありません。
伝説の土地
(T):あなたのマナ・プールに(1)を加える。
(1)(U),(T):あなたの墓地にあるアーティファクト・カード1枚を対象とし、それをあなたのライブラリーの一番上に置く。
そこで白羽の矢が立つのがこの《不死の霊薬》です!
特定の相手に有効なカードを一枚挿しておき、相手に応じて《テゼレット》でサーチして場に出します。相手がようやくそれを対処できたところで、《不死の霊薬》によってそのカードを墓地からライブラリーに戻し、再びサーチして場に出しましょう。相手はどんな顔をするか、楽しみではありませんか。このような《不死の霊薬》の動きによって、デッキの中の一枚挿しの枚数を水増しすることが可能になるのです。
理由は違いますが、サーチ前提の一枚挿しと墓地回収によるライブラリー修復というエンジンは、以前受信したウギンの目とエルドラージの使い方にも通じるところがありますね。
(http://mtg2384.diarynote.jp/201005232206083711/)
そして上記の通り、不十分とは言え《不死の霊薬》自体が単体でも高速ビートダウンに対する対策カードとして効果があるのが素晴らしいところです。
つまりこの《不死の霊薬》は、『テゼレッター』などのサーチ前提の一枚挿しの多いデッキに厚みを持たせるためのカードだということです。
・・・いや、やっぱ無理がありますね、すんません。
高速ビートなら《テゼレット》は一蹴されるし、墓地とライブラリーを回すより釣った方が早いし。
何より《不死の霊薬》をサーチしたいと思えない。
でもこれ以外に《不死の霊薬》の効果の意味が見つからんかったんだ・・・
教えてえろいひと!



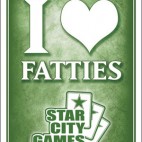
コメント
フィニッシャーフェリダー!
ロマンが溢れすぎて涙まで溢れてきますよ・・・
>ペンタバイトさん
う~むしかし、ライフゲインをしたいだけなら白いカードを使った方がいいわけで・・・
なんでウィザーズがあんなややこしい効果を付けてきたのかなーって思っちゃいました。